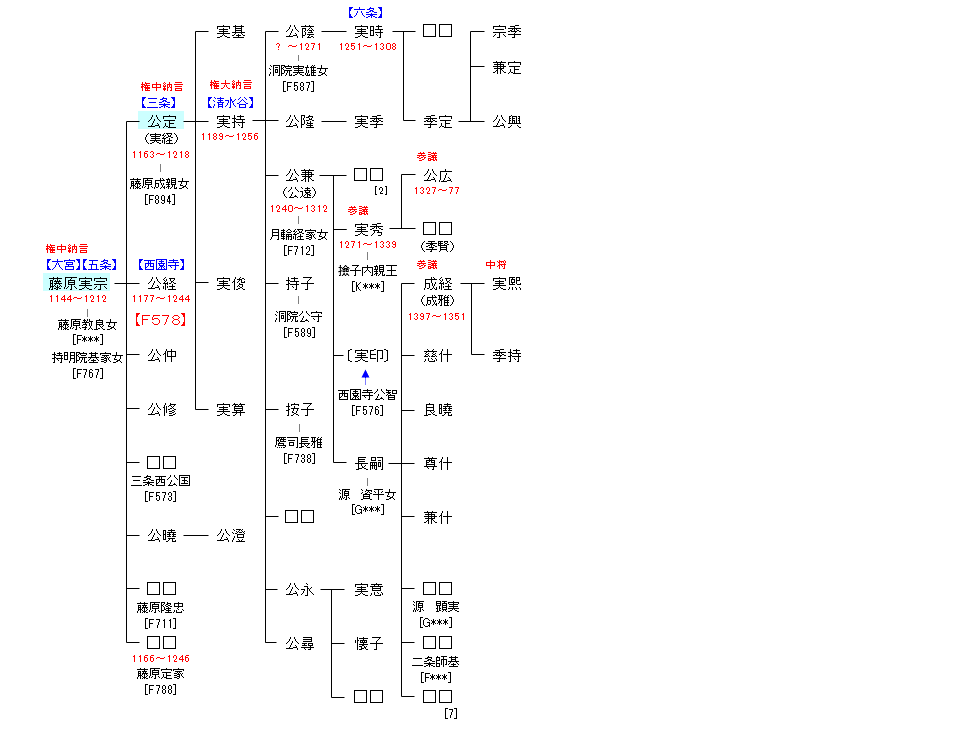|
久安4年(1148年)1月7日、叙爵。久寿2年(1155年)11月12日、従五位上に昇叙し、以降、順調に昇進。承安3年(1173年)4月8日、父の喪に服す。同年6月12日、蔵人頭に復任する。安元2年(1176年)12月5日、参議に任ぜられる。寿永2年(1183年)1月22日には権中納言に任ぜられる。文治元年(1185年)12月25日、正二位に昇叙。
文治5年(1189年)7月10日、権大納言に任ぜられる。建久2年(1191年)3月28日、大納言に転正。建久9年(1198年)4月23日、大嘗会検校に補されるが母の喪に服す。同年12月には復任した。元久2年(1205年)11月24日、内大臣に任ぜられる。建永元年(1206年)3月13日、内大臣を辞退し、11月27日、出家。建暦2年(1212年)10月29日、薨去。
後に西園寺家と称されることになる藤原通季の子孫の中で、実宗は初めて内大臣に任ぜられたのであるが、その過程には少なからず紆余曲折があった。元久2年(1205年)当時、藤原隆忠が右大臣に転任後の内大臣は空席となっていた。同年6月に実宗よりも席次が下であった源通資が内大臣を望んでいると実宗は耳にする。同月19日には八条院が通資を内大臣に任ずるよう後鳥羽院に迫ったと実宗は伝え聞いたのだが、もし通資が実宗を越えて内大臣に任ぜられた場合にはどのようにすれば良いかと、実宗は娘婿であった藤原定家をわざわざ自邸に招いて相談したのである。定家はそのようなことになった場合は籠居すれば良い、と返答している。結局、通資は内大臣に任ぜられることなく同年7月8日に薨去するが、実宗が内大臣に任ぜられたのは同年11月24日である。
実宗が藤原師長の弟子として琵琶の秘曲伝授を受けたことは『文机談』にも見えるが、実宗の日記『六条入道内大臣殿御記』によると、建久3年(1192年)6月27日、藤原師長から啄木を伝授された時の様子が詳しく記されている。さらに実宗自身が師として建久5年(1194年)3月1日には守貞親王に石上流泉を、正治2年(1200年)3月14日には同じく守貞親王に啄木を伝授したことが記されている。ただし、後鳥羽院が自ら琵琶を学ぼうとして琵琶の御師を選ぼうとした際に、実宗と藤原兼実が候補に挙げられて兼実が政治的に失脚したことで実宗が優位となっていたが、院の母である七条院の従兄弟で同じ師長の弟子であった藤原定輔が涙ながらに懇願したために定輔が選ばれた。外戚出身で院近臣の定輔が選ばれたことを知った実宗は憤りの余り「いまより後は家中に琵琶をとり入るべからず」と宣言したが、結局は実宗本人が琵琶を絶つことができず、儀式や行事の際には定輔と実宗(あるいは公経)が交替で琵琶の奏者を務めている。西園寺家はこののち琵琶秘曲伝授を代々受け継いでいくことになるが、その基礎を実宗が固めたということができる。
|
仁安2年(1167年)5歳にして叙爵。寿永元年12月(1183年1月)に従五位上、寿永2年(1183年)侍従、文治3年(1187年)阿波介、文治4年(1188年)正五位下に昇叙。建久5年(1194年)には左近衛少将,蔵人を兼任する。
建久6年(1195年)2月、遠江介を兼任。12月(1196年1月)には左少弁に任ぜられる。建久8年(1197年)正月、従四位下に叙される。建久9年12月(1199年1月)には左中弁に転じ、正治元年(1199年)に従四位上・修理左宮城使、正治3年(1201年)正四位下、改建仁元年(1201年)8月に右大弁・蔵人頭、翌建仁2年(1202年)阿波権守を兼ねる。
建仁2年(1202年)7月23日、参議に任ぜられ、翌年には従三位に昇る。建永元年(1206年)、備前権守,左大弁,勘解由次官を兼ね、位階は正三位に昇るも子の実基が妖言に関係したとして佐渡国に配流となった。
建暦元年(1211年)に帰京し、民部卿を務める。翌年、参議に復する。建保4年(1216年)従二位・権中納言に至る。建保6年(1218年)出家。
|