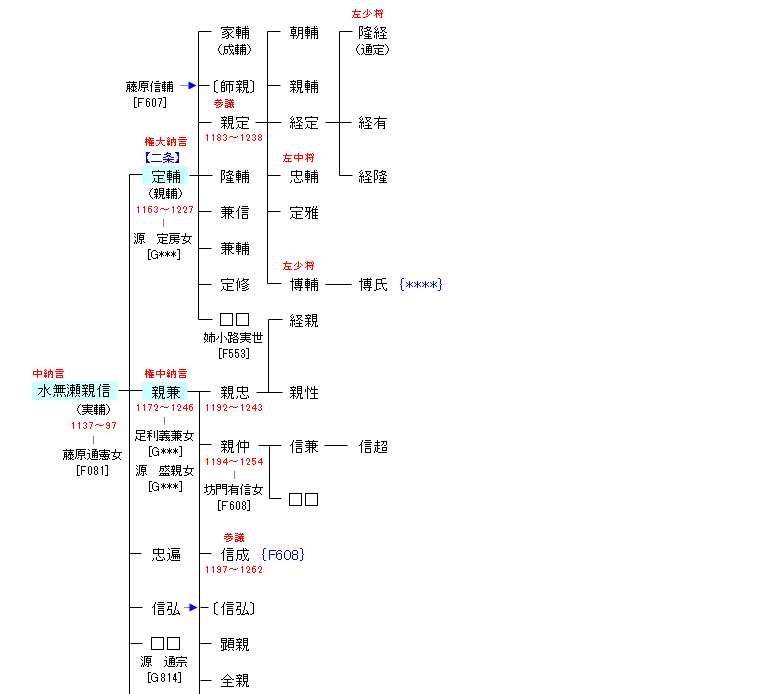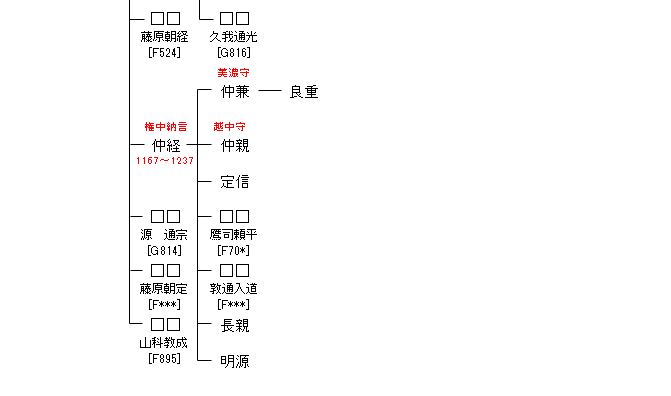|
久安4年(1148年)に叙爵。以後、備中国,伊予国などの国司や内蔵頭を歴任する。兄達と同様に後白河法皇の近臣として朝廷における地歩を固め、安元2年(1176年)に太宰大弐、翌治承元年(1177年)に従三位に上り公卿に列する。しかし、治承3年(1179年)の治承三年の政変において平清盛によって解官され、一旦朝政からの退隠を余儀なくされる。翌治承4年(1180年)に復帰すると、再び院近臣としての活動に勤しみ、寿永2年(1183年)には正三位・修理大夫、次いで参議に補される。寿永3年(1184年)の一ノ谷の戦いの直前には、法皇の意を受け平宗盛との和平交渉にも当たったと言われる。
その後も文治4年(1188年)従二位、文治5年(1189年)美作権守・権中納言、建久元年(1190年)に正二位、同2年(1191年)には中納言に任ずるが、これを極官として同8年に出家し、程なく薨去した。その子孫は中世から近世において羽林家として家格を保ち、明治維新に至っている。
|
二条大納言、また二条帥入道と号す。妙音院相国・藤原師長の琵琶の高弟として知られる。
承安2年(1172年)1月5日、叙爵し、治承5年(1181年)3月26日、周防守。文治3年(1187年)5月4日、修理大夫。文治6年(1190年)1月24日、内蔵頭を兼ねる。
建久9年(1198年)11月25日、正三位。正治2年(1200年)4月1日、参議。建仁2年(1202年)7月23日、権中納言。元久2年(1205年)11月24日、中納言。承元3年(1209年)4月10日、権大納言。承元5年(1211年)1月18日、権大納言を辞した。
建保5年(1217年)6月29日、大宰権帥。承久3年(1221年)7月、恐懼に処せられ、閏10月9日、出仕を免ぜられる。12月10日、太宰権帥を止める。本座勅授を許される。貞応2年(1223年)2月17日、出家し、嘉禄3年(1227年)7月9日、死去。
『文机談』によると、定輔は藤原師長の5人の高弟の一人として挙げられている。しかも他の琵琶の名手達を差し置いて後鳥羽院,順徳院の師範として選ばれたことが特筆されている。順徳院の時代に累代の名器である「玄上」を弾いたことのある3人の内の1人として定輔の名が挙げられている。しかも定輔は「玄上」を3度弾いたとされる。
定輔は単に琵琶の演奏に秀でていただけではなく、琵琶という楽器そのものにも詳しかったと伝わっている。しかし一方では定輔の息子達はあまり琵琶に熱心ではなかったようである。
なお、芸能面において後鳥羽院政を支える存在であった一方で、正二位権大納言にまで昇りながら、院や内裏での会議などに出席・発言した記録は少なく、政治的業績に関しては皆無に近かった。定輔は琵琶を巡る西園寺実宗や藤原孝道との確執や政治的業績がなく、芸能の才だけで昇進を重ねた経緯から多くの公家たちの反感を買っていたらしく、定輔が亡くなった時に藤原定家は「子供の頃より讒言を為し、謀詐によって二代の天皇の琵琶の帝師になった」と酷評している。
|